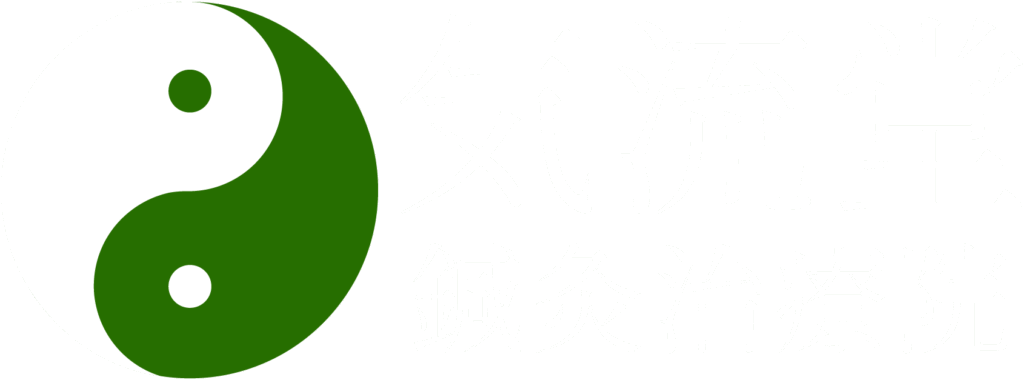生物学者の福岡伸一氏の、生命現象はすべて「動的平衡」の原理に則っているという説に深く共感して、氏の著作(講演も数回視聴)のほとんどすべてを読んで、現在再読中です。
読んでいて、心底感心させられるのは、氏の物事の原理を的確にとらえる視点と、その博学(理系の分野だけでなく)と、その文章の美しさです。理系的な頭脳でシステマティックに捉えているのですが、氏のグランドセオリーである、「ピュシス=生命」と「ロゴス=論理」がうまく共生しあって、見事な調和を生み出していて、読後にいつも、他の読書で得られない深い了承感と、新たな気づきを得ることができます。
この度の読書で特に強く共感したのは、すべての生き物は、地球上のすべての原理である「エントロピー増大」の原理という大きな潮流の中にあって、つかの間の秩序=「淀み」現象に過ぎない。それは時間の流れの中にあって存在するものであり、エントロピー増大に逆らって、作ることと壊すことのバランスが、絶妙なバランスが成立した瞬間のみ、生命現象の秩序が生み出される。そして、大事なのは、常にわずかだけ「壊す>作る」の動的なバランスを保ち続けなければならない。その瞬間が成立するバランスの状態では、瞬間に、エントロピー増大の不可逆的な流れが、一瞬逆方向に行き、生命現象が生み出される。しかし、時間とともに、やがて、すべての生命は、エントロピー増大の流れに押し流され、やがて死を迎える。つかの間の生命を、子孫に受け継いで。
ノーベル賞を受賞した大隅氏の研究である「オートファジー」は、まさに、細胞が、積極的に壊すという機能を有しているということを証明したものです。
「何かを得たいのならば、今持っているものを手放さなければならない。」
私が、モットーとしているこのことわざも、動的平衡原理を表しているということに気づきました。
秩序を維持するためには、少しずつ、システムに溜まった滓をかきだしていかなければならない。
毎日、せっせと築50年の自宅を掃除する際にも、動的平衡を意識するようになりました。