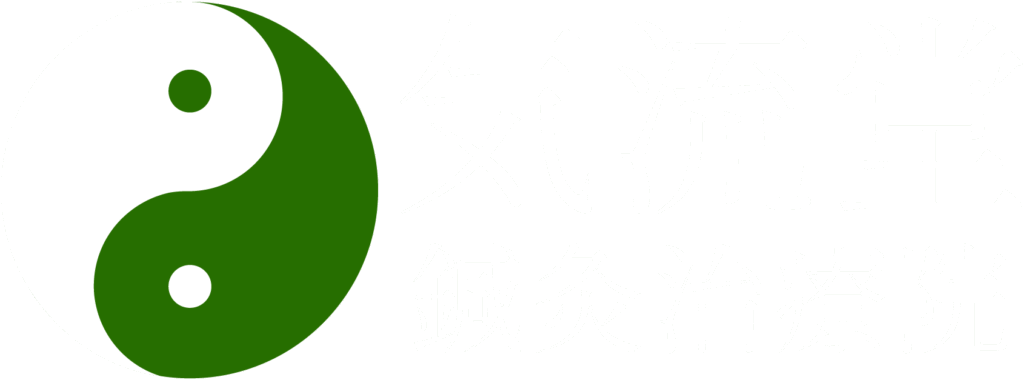堀川恵子著「透析を止める日」を読んで、透析患者の実情の過酷さを知りました。
堀川氏の夫であるテレビディレクターの林氏は、30代前半から遺伝性の腎疾患を発病、30代後半からは透析治療を始めました。
40代後半で二人は結婚し、自身も永澤紀夫死刑囚の丹念な取材をもとに、骨太のテレビ番組を製作していた堀川氏は、過酷なテレビ制作という現場で、透析治療のハンディを負いながらも、それを現場ではひた隠しにして、番組制作に命を燃やす夫の姿に打たれ、夫唱婦随で、透析治療に関わっていきました。
そしてジャーナリストとして、透析治療の実態ー数年で打ち切られる状況になり、腎臓移植をしなければ、それは死を意味するものであるということ、透析治療の過酷さ、腎疾患患者の終末期医療の不備等々ー、プロでありながら、情報収集に苦労し、夫の急速に進行する病状について看病する日々に翻弄されつづけました。
私自身、透析に2種類(血液透析、腹膜透析)があり、その選択如何で、その後の予後に大きな影響を与えること、腎移植後にも、移植腎の寿命があること、透析が、かくも苦痛に満ちた治療であるのかということを、初めて知りました。
夫の死までの腎治療の現状を、読むものが胸苦しくなるほど実態に迫ったものであるだけに、実際にそばで体感し、死力を尽くして、共に生き延びようと戦った日々を振り返る作業は、地獄のような苦しみだったと思います。
後半は、夫の治療でずっと腑に落ちず悩まされ続けた日本の腎治療の実態を、丹念に取材し、問題提起と、患者の立場に立った治療の可能性を示唆しています。
通り一遍の病の理解ではなく、このように当時者目線から語られる病の実態を知ることの大切さを痛感しました。