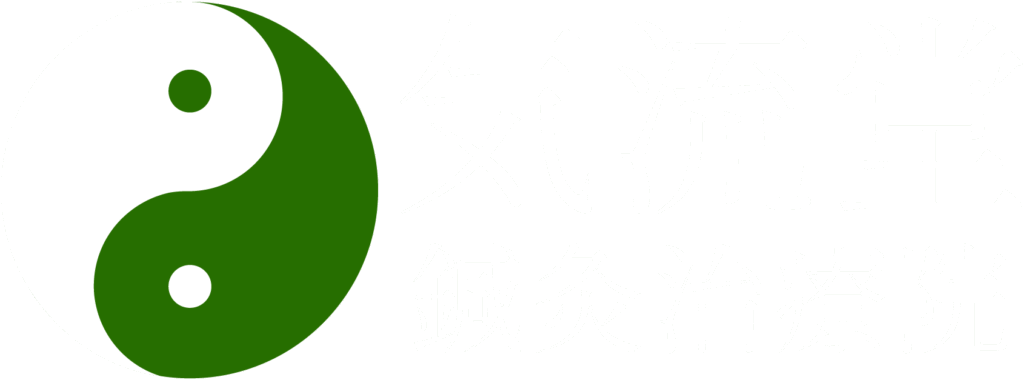石川結貴著「家で死ぬということ」を読んで、ピンピンコロリ思想が、全くの幻想であり、ピンピンはあっても、その先のコロリは、理想のようには決して訪れないということがよくわかりました。
著者は、離れて住む90歳になる一人暮らしの父親の最期を看取ったのですが、昭和一桁生まれの気丈で、頑固な男性である、父親の想いを尊重しながらも、現実とかけ離れ、最新のテクノロジーによる情報収集からも隔たってしまっている高齢者の最期を迎えることの困難を身をもって体験しました。
腎機能障害であるにも関わらず、がんとして人工透析はせず、自然なままに死ぬことを主張する父親。
しかし現実に、透析治療を拒否するということは、医療との接点を失うということで、腎機能が衰えて身体が不自由になり、様々な症状が引き起こす苦痛、そして、老化に伴う身体や生活困難は、決して父親の思い描く「ひとりで」真っ当することは、現代の家族関係、地域での医療資源、金銭、人的不足等様々な要因により、困難であるということです。
私自身、現在認知症で、介護度2、91歳の母親を実家に毎週末帰省して介護していますが、認知症ゆえに引き起こす様々なトラブルや生活困難に対処する中で、この本に書かれているような親の最期を看取るという現実を改めて再考しました。
昨今孤立死が取り上げられていますが、たとえ、一人で死んだとしても、そこに至るまで、また死後も、決して一人では対処できないというのが、個人の人間の死であるということ。
それゆえ、誰もが訪れる死という現実を、希望や理想によって覆い隠すのではなく、ありのままに見据えて、それとどう向き合い、一人の人間の死を、その人をとりまく人々の共同作業として捉えていく視点が大切だと思いました。